バドミントンラケットが折れてしまう原因は、使用頻度の高さや扱い方、ガットの張り方など様々です。壊れてしまった時はショックですが、修理や買い替えなどの対処法があります。
このページでは、折れる原因と予防策、折れにくいラケットの選び方や長持ちさせるメンテナンス方法を2025年最新情報で解説します。さらに、予算やプレースタイルに合わせた新調のポイントや専門家おすすめのケア方法も紹介し、これらの知識を活かして快適なプレーを続けましょう。皆さんが安心してバドミントンを楽しめるようにサポートします。
バドミントンラケットが折れる原因と対策
バドミントンラケットが折れる原因は複数あります。強い衝撃が加わるとフレームにヒビが入ったり折れたりしやすくなります。また、ガットの張り加減は適正範囲でなければラケットに過度な圧力がかかり、折れてしまうこともあります。長期間同じラケットを使い続けたり、雨ざらしや直射日光の下で放置したりすることもラケット劣化の原因です。
以下ではこれらの主な原因を詳しく見ていき、折れを防ぐためのポイントを解説します。
衝撃や落下による折れ
バドミントンラケットのフレームは細いカーボン繊維でできているため、外部からの衝撃にとても弱い特徴があります。自分や練習相手にラケットをぶつけたり、スイング中にラケットを地面に落としてしまったりすると、フレームにヒビが入ったり折れたりすることがあるのです。特に、ラケット同士がぶつかるような強い衝撃は折れるリスクが高くなります。
予防策としては、ラケット使用時に周囲への注意を払うほか、使用しない時はケースに入れて保護することが基本です。
知らず知らずのうちに起こるちょっとした衝撃でもダメージになることがあります。例えば、ラケットを立てかけていた場所に足をぶつけたり、机の角に当ててしまったりすると、フレームに小さなヒビが入ることがあります。これらのヒビは徐々に広がり、最終的に折れてしまう原因になるため、ラケットは常に扱いに配慮し、ささいな衝突でも注意深くチェックする習慣をつけましょう。
ガットテンションによる負荷
ガットのテンション設定もラケットの破損に直結します。各ラケットには推奨の張力範囲があり、これを超えてガットを強く張ると、フレームに常に大きな力がかかり折れやすくなります。特に大会志向のプレーヤーは飛びを追求して高テンションにしがちですが、余計なテンションはかえってラケットを痛める原因になります。ガットが切れた状態で放置するのも同様にフレームに負荷が集中するため、切れたら早めに張り替えることが重要です。
使用頻度が高い人は、推奨テンションよりやや低めに設定するなど工夫すると良いでしょう。
不適切な保管・取り扱い
ラケットを不適切に扱うと、素材が劣化して予期せず折れることがあります。例えば、真夏の暑い車内に長時間置きっぱなしにしたり、ラケットの上に重いものを乗せてしまったりすると、フレームの樹脂や継ぎ目がダメージを受けます。ガットが切れたまま放置するのも、フレームの一部にテンションがかかり続けるため危険です。
これらを防ぐには、使用後は必ずケースに入れて保護し、湿度や高温による劣化を避けるのが基本です。
経年劣化と使用頻度
ラケットは長期間使用すると金属疲労(フレームの疲労破壊)を起こすことがあります。練習頻度が高いほどラケット寿命が短くなる傾向にあり、週1~2回なら5~10年、週3~4回なら2~3年、毎日練習する選手なら1年程度で買い替え検討という目安があります。これは使用の繰り返しや張力によってフレーム素材に微小なダメージが蓄積するためです。以下の表に、一般的な練習頻度とラケット寿命の目安を示します。
| 練習頻度 | ラケット寿命の目安 |
|---|---|
| 週1~2回 | 約5~10年 |
| 週3~4回 | 約2~3年 |
| 毎日練習 | 約1年以内 |
折れやすいラケットの特徴と選び方
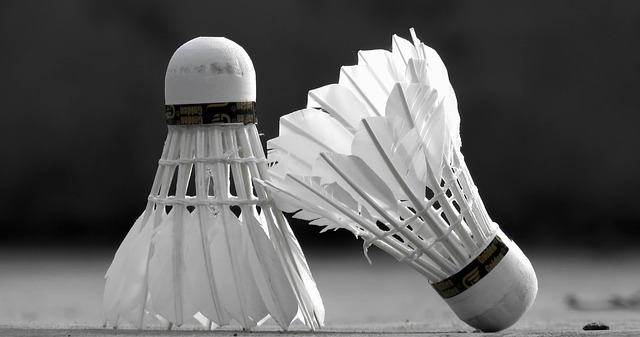
ラケット自体の性質によっても折れやすさが変わります。素材やフレーム構造、重さ、価格帯などで耐久性に違いがあるため、自分のレベルや用途に合ったラケットを選ぶことが大切です。以下に、折れにくいラケットを見極めるポイントと初心者・上級者それぞれに適した選び方を解説します。
素材とフレーム構造の違い
ラケットの素材やフレーム形状は耐久性に大きく影響します。一般的に、高級モデルは軽量カーボン素材を多用していますが、衝撃には弱く壊れやすい場合があります。一方、初心者向けの比較的安価なラケットは太いアルミフレームなど堅牢性を重視する素材で作られており、多少乱暴に扱っても折れにくいメリットがあります。
また、中空構造や肉厚設計のフレームは耐久性が高く、逆に極薄フレームは強い負荷に弱い傾向です。
重さと耐久性の関係
ラケットの重さ(グラム数)にも耐久性とのトレードオフがあります。重量級ラケットはフレームが太く頑丈で、多少強く打っても変形や折れにくい特徴があります。ただし重いラケットは扱いが大変なのでスイングスピードが上がらず、プレーを難しく感じる場合があります。逆に軽量ラケットは振り抜きやすくスピード面で有利ですが、フレームが薄く衝撃に弱い分、耐久性は低い傾向です。自分の筋力やプレースタイルと照らし合わせて、重さと耐久性のバランスを考えることが大切です。
ブランド・価格と耐久性
価格が高いラケットは性能面で優れていますが、必ずしも耐久性が高いわけではありません。プロモデルなど高額ラケットは軽量化のために薄いフレームが多く、通常使用でも折れやすい場合があります。逆に、低価格帯のラケットは素材を厚めにして丈夫さを重視する設計がされていることが多く、耐久性という点ではコストパフォーマンスに優れています。選ぶ際は、ラケットの評価やレビューで耐久性に関する情報をチェックすると安心です。
レベル別・用途別の選び方
ビギナーやジュニア選手の場合は、まずは耐久性を重視したモデルを選ぶと安心です。初心者向けラケットの多くはフレームが丈夫で扱いやすいため、雑に扱っても折れにくい設計になっています。一方、上級者は軽量性や操作性を優先しがちですが、ヘビーなスイングをする選手は少し厚みのあるフレームを使うのがおすすめです。また、パワー型の選手はやや重めのラケット、速い連続スマッシュを打ちたい選手は振り抜きのよい軽量ラケットが向いており、それぞれ耐久性とのバランスを取りましょう。
折れたラケットの修理・買い替えガイド

ラケットが折れてしまった場合、修理するか新しいラケットに買い換えるかを検討することになります。近年は専門の修理ショップも増えており、折れた部分を補強したりパーツ交換したりすることで本体を復活させられるケースがあります。ただし技術と部品が必要なため費用がかさむこともあるため、修理と新品購入のメリット・デメリットを比較して判断しましょう。以下では、修理費用の相場や手順、新しいラケットを選ぶ際のポイント、中古や下取りの利用法などを解説します。
修理業者の利用と費用
最近ではラケット修理を専門とするショップやサービスが増えています。一般的には折れたフレーム部を接着・補強して修復する形で、費用は5,000円程度が目安です。高価なラケットであれば修理のメリットが大きく、修理後も大会で使用できることがあります。ただし、修理可能な範囲には限界があり、フレーム全体を交換するわけではないので元どおりの性能には戻せません。
修理に出す前には、見積もりを取り、ラケット本体の状態や費用対効果を確認しておきましょう。
新品購入の検討ポイント
打ち切りにして新品を購入する場合、前のラケット使用経験を踏まえて選びましょう。まずは予算内で同程度かそれ以上のスペックのものを検討します。多くの修理店でも新製品の案内があり、同じメーカー・モデルの後継機種を紹介してくれることもあります。予算や使い慣れた形状、性能を優先しつつ、折れた原因が打ち方やテンションにあるなら、次はやや耐久性を重視した少し硬めのフレームを試してみると安心です。
中古・下取りの活用
費用を抑えたい場合や型落ちラケットを狙いたい場合には、中古品や下取りサービスを利用するのも一つの方法です。いくつかの専門ショップやオンラインマーケットでは、状態の良い中古ラケットを比較的安く入手できます。また、使用していたラケットを下取りに出せるショップなら、新品購入時に割引が適用される場合もあります。ただし、折れたラケットを下取りしてもらえることは少ないので、事前に条件を確認しておきましょう。
ラケットを長持ちさせるメンテナンス方法
折れを防ぐには日頃のメンテナンスが最も重要です。ラケットを清潔に保つだけでなく、張替や保管方法についても最新の注意を払うことで耐久性が向上します。このセクションでは、使用後の手入れから環境対策まで、ラケットを長持ちさせるための具体的な方法を紹介します。
使用後の清掃と保管
ラケットの寿命を延ばすには、使用後のケアが大切です。汗や埃がフレームに付着したまま放置すると素材の劣化を早めるため、プレー後は柔らかい布でガットとフレームを拭いておきましょう。特に高温多湿の環境では錆や樹脂劣化が進みやすいので、ラケットは通気性の良い場所で乾かしてから保管します。また、持ち運び時はケースやカバーを使い、直射日光や重い荷物の圧力から守るようにしてください。
- 使用後は柔らかい布でフレームとガットの汚れや汗を拭き取る
- 湿気を避け、カビが生えない場所で完全に乾燥させる
- 直射日光や熱源の近くに置かず、専用ケースに収納して衝撃から守る
適切なガットテンション管理
ガットの張力は安全策も兼ねています。長期間同じテンションのまま使用しているとガットの摩耗だけでなく、フレームへのテンションも徐々に変化します。定期的にガットの状態をチェックして、へたっている場合は張り替えましょう。また、前述の通りテンションは使用レベルに合わせて設定し、オーバータイトにならないよう注意します。新品張りなどでラケットに合わせた適正テンション設定を守ることが大切です。
高温・低温環境での注意
ラケット保管で特に気をつけたいのが高温・低温環境です。夏場の車内は60℃近くまで上がることもあり、このような急激な温度上昇はフレームの樹脂を劣化させます。同様に、気温の低い場所に放置するとカーボンが変形しやすく危険です。極端な温度下で保管するのは避け、温度変化の少ない室内でケースに入れて保管する習慣をつけましょう。
定期点検と見極め時期
ラケットは定期的に目視点検して、不具合がないか確認しましょう。フレームに小さなヒビや変形が見られたら、そのラケットは寿命間近と考えられます。早めに異変に気づけば、大事な試合の直前でも突然折れるリスクを減らせます。一般に、ひび割れを見つけたら同試合や練習での使用は避け、交換を検討してください。定期的なチェックを習慣付けることで、安心してプレーを続けやすくなります。
まとめ

- ラケットの折れる原因は「強い衝撃」「高テンションによる負荷」「不適切な保管」「経年劣化」の4点が代表的です。
- 折れにくいラケットを選ぶには、耐久性の高い素材や太めのフレーム設計をチェックし、初心者は耐久性重視の丈夫なモデルから検討すると安心です。
- 折れた場合は、専門店での修理(約5,000円程度)と新品購入のメリット・デメリットを比較しましょう。高価なラケットなら修理も選択肢になります。
- 日頃のメンテナンス(使用後の清掃・乾燥、適切な保管、ガット張替えなど)を行うことでラケット寿命を延ばし、安全にプレーが続けられます。
これらのポイントを意識すれば、バドミントンを安心して楽しみながらラケットを長持ちさせることができます。
コメント