バドミントンラケットは高価で高性能な一方、軽量設計のため思わぬ衝撃で折れてしまうことがあります。折れてしまう原因を把握し、予防や対処法を知っておくことは重要です。本記事では2025年の最新情報を踏まえ、ラケットが折れる原因や予防策、折れた後の修理・買い替えについて詳しく解説します。
目次
バドミントン ラケット 折れる 原因と対策
バドミントンラケットが折れてしまう原因は大きく分けて外部からの衝撃と内部からの負荷、そして不適切な取り扱いの三つです。練習や試合中にラケットを他の物にぶつけたり、ガットを張りすぎたりするとラケット本体に大きな力がかかり、フレームが折れてしまうことがあります。また直射日光の車内放置やガット切れ放置なども気付かないうちにフレームに負担をかけ、折れる原因になり得ます。これらの原因を理解し、発生を未然に防ぐ対策を取ることが大切です。
ラケットが折れる主な原因
まず一番の原因はラケットへの衝撃です。試合中や練習中にラケット同士がぶつかったり、足や床に当ててしまったりすると一瞬でフレームにひびが入ったり折れてしまいます。特にパワーの強いスマッシュや激しいラリーではラケットに大きな負荷がかかるため注意が必要です。
次にガット張力もラケットが折れる原因になります。ラケットにはメーカー推奨の上限テンションが設定されていますが、これを超えて強く張りすぎるとフレームが耐え切れずに折れることがあります。特に上級者向けの硬めのラケットではガットテンションを高める傾向がありますが、その分フレームへの負担も大きくなります。
また、不適切な取り扱いや環境も原因となります。たとえば車の夏場の高温状態に放置するとフレーム接着剤が劣化しますし、ガットが切れたまま放置するとラケットの片側だけに力がかかりフレームを歪めてしまいます。これらは一見関係ないように思えますが、知らず知らずのうちにラケットを弱らせてしまいます。
ラケットを折れにくくする対策
上記の原因を避けるために、いくつかのポイントを意識すればラケットの折れを予防できます。まず練習や試合では衝撃をできるだけ避けることが重要です。ダブルスでのスマッシュの打ち合いではパートナー同士のラケットがぶつからないようこまめに声を掛け合い、足でラケットを蹴ってしまわない注意をしましょう。
次にガットテンションはラケットの適正範囲内で管理しましょう。一般的には20~28ポンドが主流ですが、メーカーの推奨値を参考にし、自己流で張りすぎないようにしてください。テンションを高めた場合は練習後にフレームに亀裂が入っていないか確認し、少しでも心配な際はガットを緩めるか交換してフレームへの負荷を軽減します。
さらに、日常の取り扱いでも注意点があります。ガットが切れたらすぐに処理し、放置しないこと。また、ラケットバッグにバッグを詰め込みすぎないようにし、硬い物は別のバッグに分けましょう。ラケットバッグにラケットを入れたまま引っ張ったり、つまずいたりするとフレームに大きな歪みが生じます。車内ではエアコンの効いた涼しい場所に置くなど、ラケットが高温になる環境を避けることも大切です。
ラケットが折れやすい状況や予防策

ラケットが折れやすい場面や条件を知っておくと、事前にリスクを回避できます。練習や試合中に起こりやすい状況や、うっかり発生しがちな要因ごとに解説します。
ダブルスでのラケット衝突
ダブルスでは自分とペアの間にスマッシュが飛んできた際、互いに打とうとしてラケット同士が激突するケースが多く見られます。お互いに全力で振るため衝撃も相当で、これだけでフレームが一瞬で折れてしまうことがあります。特に合わせが慣れていないペアや、パワーの差がある場合は衝突リスクが高まります。
対策としては、事前に声を掛け合う習慣をつけたり、練習でペアのスイングスタイルを把握したりすることが有効です。自分よりもパワーが強い相手と組む場合は、より慎重に位置を調整することで衝突リスクを減らせます。万が一衝突してしまったら、その時点でラケットに傷やヒビが入っていないかすぐ確認し、懸念がある場合は使用を中止しましょう。
高張力ガットとフレームへの負荷
ガットを高いテンションで張ると、ラケットフレームに常時強いテンションがかかる状態になります。このような状況では、ほんの小さな外部衝撃でも折れやすくなります。最近の2025年モデルではフレームの強度も向上しつつありますが、それでもメーカー指定を超えたガット張りは避けるべきです。
特に自分で手張りする場合や、テンション基準がわからない人は、ショップでのガット張り替えを依頼するのがおすすめです。多くのラケットには適正テンション(例:20~25ポンド)が記載されているため、その範囲内で張ってもらいましょう。定期的にラケットのフレームに亀裂がないかチェックし、ガット張り替え時にも注意深く確認する習慣をつけると安心です。
誤った保管・管理方法
無造作にラケットを床に置いたり、ラケットバッグに荷物を詰め込みすぎたりすると、思わぬ形でフレームに負担がかかる場合があります。子どもが体育館の床に置いて踏んでしまったり、ラケットケースに着替えやタオルを詰め込んで背負ったりすると、知らない間にフレームが歪んでしまいます。
また、夏場の車内は高温になりやすく、ラケットの接着剤や素材が劣化して折れる原因になります。車に長時間置きっぱなしにしないようにしましょう。これらは一見ラケットのプレーとは無関係な場面ですが、フレームに余計な負荷をかけないためにも、正しい保管と管理方法を心がけることが重要です。
折れたラケットの修理方法と買い替え

万が一ラケットが折れてしまった場合、修理をするか新品に買い替えるかの二択になります。どちらを選ぶべきかはラケットの価格や使用頻度、新製品への思い入れなどにより変わります。それぞれの方法のポイントや費用を確認しましょう。
ラケット修理の方法と費用
現在ではバドミントンラケット専門の修理業者が存在し、フレーム交換や修理を依頼できます。修理費用はだいたい5,000円程度が相場で、送料は別途必要な場合があります。ブランドものやお気に入りのモデルであれば、修理して使用を続ける価値はあります。特に公式戦前などで同じラケット感覚を維持したい場合は修理が便利です。
修理可能かどうかは折れ方やラケットの状態によりますが、多くの場合フレームを新品パーツと交換する形で修復されます。ただし、修理はあくまで寿命を延ばすためのものなので、何度も修理を繰り返すのはおすすめできません。修理業者はプロが行うため完成度は高いですが、まったく新品の性能に戻るわけではない点は把握しておきましょう。
新品ラケットへの買い替え時期
新しいラケットに買い替えるタイミングは人それぞれですが、以下のような場合を目安に検討すると良いでしょう。まず、ラケット自体が使用歴が長く、ガットの反発が低下してきたりフレームが全体的に劣化してきたりした場合です。折れていなくてもラケットが“ヘタる”と感じるなら、買い替えを検討すべきサインです。また、先述のように修理費用と新品価格があまり変わらない場合や、最新モデルへの興味がある場合も買い替えに適したタイミングといえます。
練習頻度が高い競技者では、一般的に1~3年でラケットを交換する人が多いようです。2025年にはさらに高強度のフレーム設計が登場しており、性能向上した最新モデルを試したい場合も買い替えを検討しましょう。購入の際は折れやすさだけでなく、用途に合ったガットテンションやシャフト硬度といった性能面も見極めることが重要です。
| 比較項目 | 修理 | 買い替え |
|---|---|---|
| 費用 | 約5,000円+送料 | 1万円以上(モデルによる) |
| 利便性 | 短期間で同じラケットを復活 | 新モデルで性能・感覚が新品に |
| 寿命 | 修理後も使えるが次第に限界が来る | 新品なので長く最新状態を維持可能 |
壊れたラケットの処分と再利用
買い替えや修理が難しい場合、折れたラケットの処分方法も考えましょう。最近ではスポーツ用品のリサイクルを行う業者やプログラムも増えています。壊れたラケットでも、素材のリサイクルに出せる場合がありますので、自治体や専門店に相談してみるとよいでしょう。
また、完全に捨ててしまう前に次のような再利用法も検討できます。年代物のラケットを練習用に使ったり、試打専用としてラケットの性能を落として使いきる方法などです。折れた部分を除けば打球自体はできることが多いので、フレームの片側が折れていない場合は思い切って短期的に練習用と割り切る手もあります。
折れにくいラケットの選び方
長く使えるラケットを選ぶことも折れ対策の一つです。素材や設計によって耐久性には違いがあるため、ラケット選びのポイントを押さえましょう。
ラケット素材と耐久性
現代のバドミントンラケットは主に高弾性カーボンやグラファイトを使っていますが、これらの素材は強度と軽さのバランスが取れています。最新モデルではカーボン繊維の層間にナノファイバーや合金素材を組み込んだフレームも登場しており、同じ重さでも飛躍的に耐久性が増しています。購入時にはフレームの素材名や技術(例:カーボンナノチューブや強化繊維など)が公表されているか確認しましょう。
高剛性素材ほど強度は高まりますが、その分スイングの衝撃を受けやすい面もあります。逆に柔軟なシャフトは衝撃吸収性が増すもののパワーロスが生じます。このあたりは
面バランスや重量バランスとともに考慮しましょう。
シャフト硬さと打ち心地
シャフトの硬さ(フレックス)もラケットの折れにくさに影響します。硬いシャフトはパワーが伝わりやすい反面、フレームに加わる衝撃も大きくなりがちです。初心者やパワーがまだ発達途上のプレーヤーは、少し柔らかめのシャフトを選ぶことで衝撃を吸収しやすく、ラケット寿命を延ばせます。
一方、上級者で打球パワーが強いプレーヤーは硬めのシャフトを好みますが、強打の際にフレームにも大きな負荷がかかるため、衝撃対策としては前述のようにラケットの取り扱いに細心の注意が必要です。また、重量バランスがヘッドヘビーのモデルはパワー重視ですが、その分ラケット先端に負担がかかりやすいので、これも注意点になります。
人気ブランド・モデルの特徴
大手ブランド(ヨネックス、ビクター、リーニンなど)からは毎年新作モデルが発表されており、耐久性向上の技術も競い合っています。例えばヨネックスの某シリーズではフレームの太さを微調整して強度を上げていたり、リーニンの別モデルでは複合素材を増やして軽量ながら丈夫に仕上げていたりします。
特定ブランドに固執せず、実際に試打して剛性や打感を確かめるのがベストです。口コミや最新レビューでは耐久性に優れると評されるモデルも参考になりますし、インターネットでは「折れにくい」と評判のシリーズ情報も見つかります。購入前にはプレーヤーのレビューや当該モデルのスペックをチェックしてみましょう。
ラケットを長持ちさせるメンテナンス方法
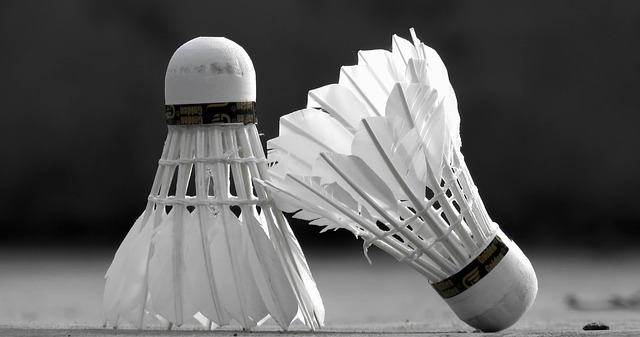
ラケットの寿命を延ばすには日頃のケアが欠かせません。取り扱い方から練習後の手入れまで、ポイントを押さえておくと大きなトラブルを防げます。
正しい保管と持ち運び方法
ラケットは使い終わったらラケットバッグに入れて保管しましょう。バッグに入れる際はラケット同士がぶつからないようカバーに差し込むか、柄の部分を揃えて収納します。チイ形にして持ち運ぶとヘッド同士が当たるため摩耗や歪みの原因になります。
- ラケットバッグに入れて持ち運ぶ
- 直射日光や高温を避けて保管する
- バッグに硬い物を詰め込まない
特に夏場は車内や体育館の熱気がこもりやすいので、温度に注意しましょう。バッグがパンパンになるほど物を詰め込むと、知らずにフレームが圧迫されてしまいます。遠征や合宿の用具は複数のバッグに分けるのが望ましいです。
ガット張り替えのタイミング
ガットは使用頻度や張力にもよりますが、目安として半年から1年ほどで張り替えるのが一般的です。特に強打でガットが傷む人は、早めの張替えが安心です。ガットが切れたら速やかに切り離し、張り替えることでフレームへの片側張力を防げます。
張り替え時は先述の推奨テンションを守るほか、フレームにヒビや傷がないかチェックしましょう。小さな傷も見逃さず、傷が深い場合は修理または買い替えを検討します。2025年にはストリンガー向けの最新ツールでもフレームを傷めにくい張替え方法が普及しており、自己張りする場合はこうした専門的な知識も参考にしてください。
日常の点検と簡単メンテ
日々の練習後にラケットを軽く拭いて汗や汚れを落とすだけでも、素材の劣化を防ぐ効果があります。グリップテープが緩くなってきたら巻き直して密着度を保ち、手汗でラケット裏に汚れがたまらないようにしましょう。
また、ラケットのフレームに小さなヒビや歪みがないか定期的に確認してください。もし亀裂が見つかった場合は、早めに専門店で診てもらうか、自分で補強テープを当てて悪化を防ぎましょう。日常の小さな手入れでも積み重ねがラケット寿命を大きく延ばすことにつながります。
まとめ
バドミントンラケットは軽さと強さを両立させた精密な道具ですが、使用環境や取り扱い次第で折れてしまうことがあります。2025年現在も新素材のラケットが出ていますが、使い方を誤れば折れるリスクはゼロになりません。本記事で紹介した原因と予防策を参考に、ラケットを丁寧に扱って長持ちさせましょう。万が一折れてしまった場合は、修理か買い替えを適切に選択し、専門店や最新モデルの情報も活用して、快適なプレーを続けてください。
コメント