テニスラケットのフレームを傷や衝撃から守る「エッジガード」。テニスラケットには純正のバンパーが付いていますが、ラケットの寿命を延ばすために追加でシールタイプのエッジガードを貼り付ける選手も増えています。一方で、「本当に必要?」と疑問に思う方も少なくありません。
こうした手法はラケット保護の観点から注目されています。本記事では、エッジガードの役割やメリット・デメリットを徹底解説し、選び方や正しい貼り方まで詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。それでは本文で詳しく見ていきましょう。
テニスラケットにエッジガードは必要?
多くの硬式テニスラケットには、メーカーからヘッド上部にバンパー(バンパーガード)が初めから装着されています。このバンパーが地面との擦り傷や打球の衝撃からフレームを保護する役割を果たすため、通常のプレーであればエッジガード無しでもある程度安心です。
しかし、練習や試合でラケットを頻繁に地面に擦りつけるような使い方をする場合や、既にバンパーの劣化が進んでいる場合には、追加でエッジガードを貼り付けて保護した方が安心できる場合があります。つまり、エッジガードが必要かどうかはプレー環境や好みによって異なります。
エッジガードとは何か
エッジガードとは、ラケットフレームの外周を保護するために貼り付けるシール状のパーツです。一般的にはウレタンやプラスチックのフィルム製で、ラケットフレームの塗装剥がれや傷を防ぎます。
自分で簡単に貼り付け・交換することができ、幅は10~15mm程度のものが多く、市販のエッジガードとして販売されています。
硬式テニスとソフトテニスの違い
硬式テニス用ラケットには一般的にヘッド上部にバンパーガードが標準搭載されていますが、ソフトテニス用ラケットは軽量化のためバンパーが付いていないものが多いのが特徴です。このため、硬式テニスではエッジガードの必要性は比較的低いですが、ソフトテニスではエッジガードを貼るのが一般的です。
| 硬式テニスラケット | ソフトテニスラケット | |
|---|---|---|
| バンパー | 標準装備 | 非装備が多い |
| エッジガード必須度 | 通常不要(あれば補強) | 保護目的で推奨 |
このように、ソフトテニスではエッジガードの装着が前提になる場合が多く、硬式テニスでは補助的な使い方にとどまることが少なくありません。
エッジガードを使う場面
エッジガードの使用場面としては、ラケットの2時・10時方向が地面に擦れやすいシーンが挙げられます。例えば、レッスン中やボール拾い時にラケットを地面に当てる動作が多い場合、フレームの塗装が擦れて剥がれてしまうことがあります。
こうした状況ではエッジガードを貼っておくとフレームへのダメージを軽減できるため、特に練習用ラケットや初級者用のラケットにはあらかじめ貼っておくことが推奨されることがあります。
エッジガードのメリット

エッジガードを使用すると得られる利点はいくつかあります。ここでは主なメリットを見ていきます。
フレーム保護とラケット寿命の延長
エッジガードの最も大きなメリットは、ラケットフレームの保護です。地面やコートとの擦れからフレームを守ることで、塗装の剥がれやフレームの亀裂を防ぎます。長期的にはラケットの寿命も延びることが期待できます。特にグロメット(ストリング出口部)の周りやフレーム端は負担がかかりやすい部分なので、エッジガードがあるとフレームの亀裂や折れを未然に防げる可能性が高まります。
カスタマイズ・デザインの自由度
エッジガードは保護目的だけでなくデザイン面でのメリットもあります。カラフルな種類が多く、ラケットのフレームカラーとコーディネートしたり、チームカラーや好みの柄で個性的に仕上げたりすることができます。実際、多くのプレーヤーが自分だけのカラーで他のプレーヤーと差別化を図っています。
また、エッジガードでフレーム全体のイメージを変えられるため、古く見えるラケットをおしゃれに見せる効果も期待できます。
初心者へのメリット
初級者やジュニアにもエッジガードの利用にはメリットがあります。経験の浅い選手はボール拾いの際などにラケットを地面に擦りやすい傾向があるため、エッジガードがあればフレームの傷つきを減らせます。
テニスを始めたばかりの方やジュニア選手には、練習用の大事なラケットをできるだけ傷つけたくないというニーズにも応えるため、エッジガードは安心感を与えるアイテムと言えます。
エッジガードのデメリット・注意点

エッジガードは多くのメリットがありますが、一方で使う際のデメリットや注意点も存在します。主なものとしては、ラケットバランスや重量への影響、貼り付けの手間、そして経年劣化といった点が挙げられます。以下では代表的なデメリットについて解説します。
バランス・重量への影響
エッジガードを貼ると、その分ラケットヘッド側に重さが増すため、スウィングウェイトが大きく変化する可能性があります。とくに競技志向の選手はバランスに敏感で、エッジガードの重さでトップヘビーに感じることがあります。一般的に、厚みや素材の重いエッジガードほど影響が大きいため、できるだけ重量の軽いものを選ぶ工夫が必要です。
貼り付けの手間と糊跡
エッジガードを貼る作業には多少の手間がかかる点もデメリットです。フレームに気泡やシワなくきれいに貼るには注意が必要で、位置調整や貼り直しが面倒に感じることがあります。また、剥がす際に粘着剤が残ったり、力を入れすぎるとフレーム表面を傷めることがあるため、扱い方には注意が必要です。
経年劣化とメンテナンス
長期間貼りっぱなしにしていると、エッジガード自体が劣化する点にも注意が必要です。使用しているうちにエッジガードの表面が白っぽく曇ったり、端から浮いてくることがあります。剥がれや傷みが進むと保護性能が低下するため、定期的に状態を確認し、劣化したら新しいものに貼り替えることをおすすめします。
エッジガードの種類と選び方
エッジガードにはメーカーや素材によっていくつかの種類があり、用途や好みに合わせて選ぶことができます。ここでは主要なエッジガードの特徴や選び方のポイントを解説します。
素材や厚みの違い
エッジガードは主にウレタンやTPUといった樹脂系の素材で作られており、厚みによって特徴が分かれます。薄手のエッジガードは重量増加を抑えることができ、トップヘビーへの影響を軽減できます。一方、厚手のタイプはフレームへの衝撃吸収性が高く、しっかり保護したい場合に適しています。
さらに、幅10mm程度の細幅タイプから15mm以上の太幅タイプまであり、自分のラケットサイズや保護したい範囲に合わせて選ぶことが大切です。
主要メーカーごとの特徴
日本国内ではヨネックスやミズノといったブランドからエッジガードが販売されています。ヨネックス製は厚手でしっかりした作りが特徴で、保護性能を重視する人に人気があります。一方ミズノ製は0.1mmと非常に薄手で軽量なので、ラケットバランスをほとんど変えずに自然な打感を重視したい人に向いています。
その他にも各社から様々なカラーやデザインのエッジガードが出ているため、見た目の好みで選ぶこともできます。
選ぶ際のポイント
エッジガードを選ぶ際は、薄型か厚型かのメリット・デメリットを理解して、自分のプレースタイルに合ったものを選びましょう。重量やバランス重視なら薄いタイプを、衝撃吸収性を重視するなら厚いタイプを選びます。
また、カラーやデザインも重要なポイントです。ダーク系は汚れが目立ちにくく、明るい色はコートでの視認性が高いという特徴があります。さらに、貼り替えが容易かどうか、粘着力の強さなども比較して選ぶとよいでしょう。
価格や入手しやすさ
エッジガードは比較的安価なアイテムで、1セット(複数本分)あたり500円前後から購入できます。スポーツ用品店やネット通販でも入手しやすく、必要に応じていつでも買い替えが可能です。少ないコストでラケットを効果的に保護できるため、コストパフォーマンスの面でも優れたアイテムと言えます。
スポーツ用品店やネット通販で入手しやすく、必要に応じていつでも買い替えが可能です。少ないコストでラケットを効果的に保護できるため、コストパフォーマンスの面でも優れたアイテムと言えます。
エッジガードの貼り方と交換方法
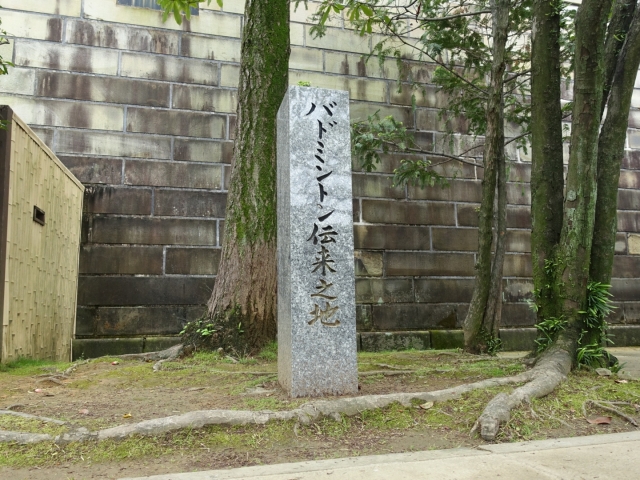
ここではエッジガードの正しい貼り方と、貼り替え・交換時のポイントを解説します。
貼付手順とコツ
まず、貼る前にフレーム表面を柔らかい布で拭いてホコリや汚れを落としておきます。手順としては、エッジガードの片側の保護フィルムを少し剥がした状態でラケットのフレーム上部(2時から10時方向)に貼り始め、少しずつ保護フィルムを剥がしながらフレームに密着させていきます。
貼り付ける際は気泡が入らないように端から指先でゆっくり押さえ、コーナー部分は慎重に曲げてなじませます。左右対称に貼ると美しく仕上がります。
剥がし方と交換時期
エッジガードを剥がすときは、フレームを傷めないよう両端の角からゆっくり引っ張って取り外します。場合によってはドライヤーの温風で糊を温めてから剥がすと、粘着剤が柔らかくなって簡単に剥がせます。
交換のタイミングとしては、エッジガードの表面にひび割れや剥がれが見られるようになったら目安です。劣化が進んだまま使用すると保護効果が下がるため、症状が出たら早めに新しいものに貼り替えるようにしましょう。
まとめ
テニスラケットにエッジガードを貼る必要性はプレースタイルや環境で異なります。硬式テニス用ラケットにはバンパーが付属しているため、通常のプレーではエッジガードがなくとも問題ありません。しかし、練習やボール拾いの際にフレームが擦れやすい場面では、エッジガードを貼っておくとラケットの傷つきを防ぎ、寿命を延ばせる可能性があります。
エッジガードのメリットはフレーム保護の他にもデザイン性の向上などがありますが、一方で、貼ることで重量が増え、バランスが変わるといったデメリットもあります。選ぶ際には厚みや色をよく比較し、自分のラケットやプレースタイルに合ったものを選びましょう。以上のポイントを参考に、テニスラケットにエッジガードが必要かどうか判断し、賢く活用してください。
コメント